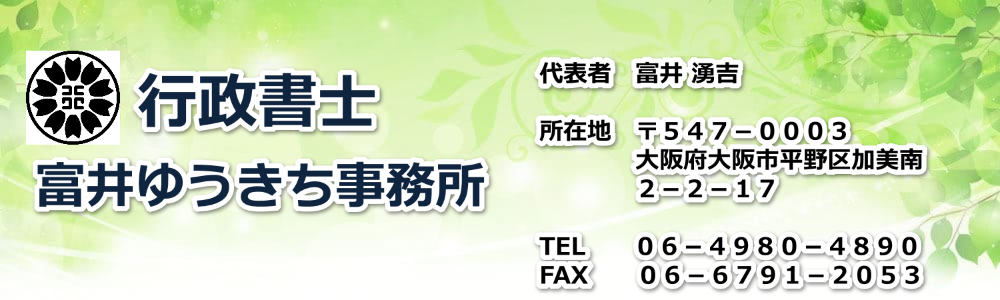後見人の よくある質問ベスト50
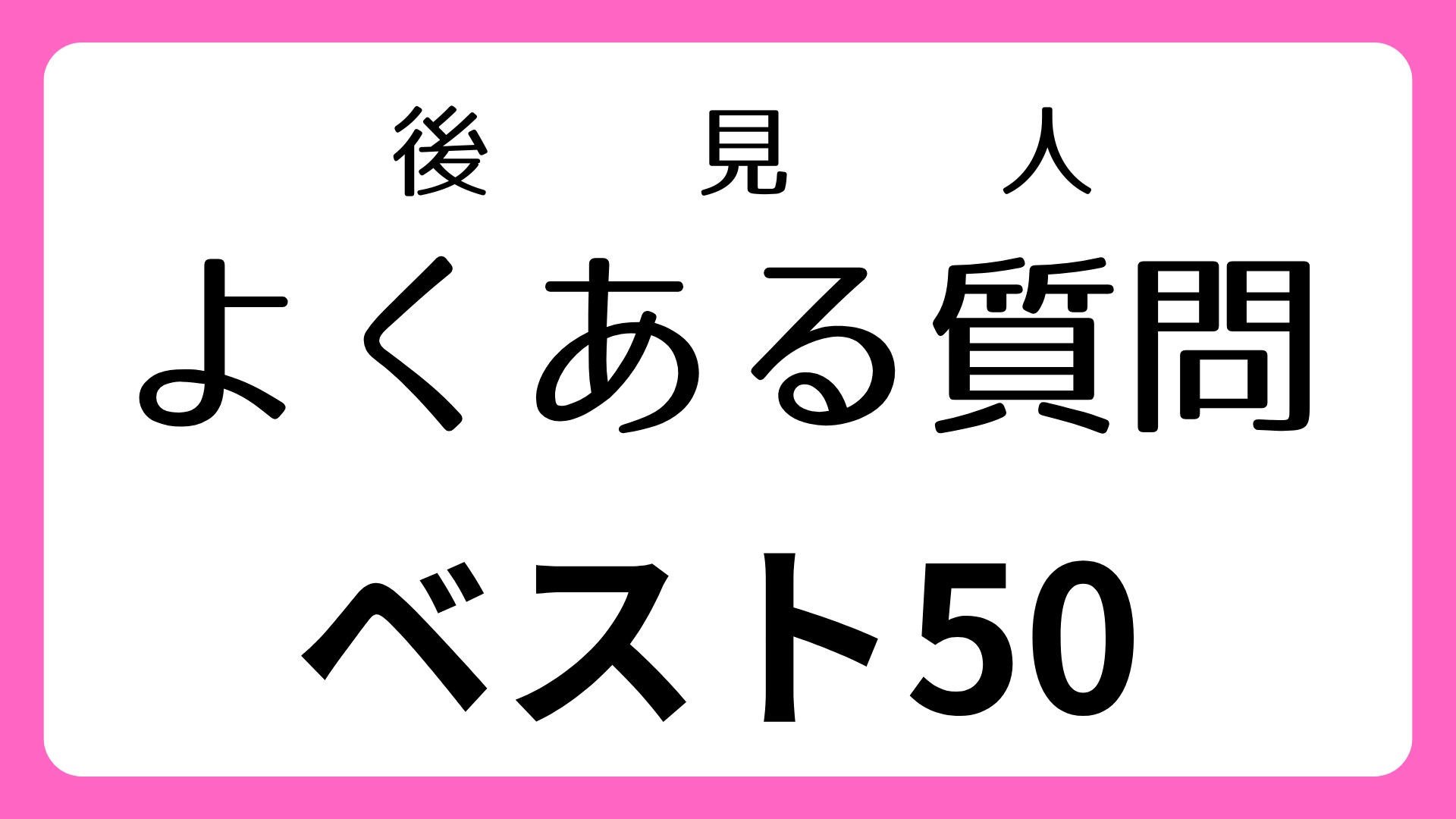
後見人の
よくある質問ベスト50
「 親が高齢になり、将来が心配… 」
「 もし自分が認知症になったら、誰が財産を管理してくれるの? 」
後見人制度は、そうした不安を解消し、
判断能力が不十分になった方を
法的に支援する大切な仕組みです。
ここでは、
後見人制度について多くの方が抱く質問ベスト50としてまとめました。
ご自身の状況やご家族の将来に照らし合わせながら、
安心して読み進めていただければ幸いです。
目 次 「 後見人の よくある質問ベスト50 」
1. 後見人って、どんな時に必要になりますか?
2. 成年後見制度とは、どんな制度ですか?
3. 法定後見制度と任意後見制度の、違いは何ですか?
4. 法定後見制度の種類には、何がありますか?
5. 後見人は、どんなことをしてくれるのですか?
6. 後見人には、誰がなれるのですか?
7. 後見人は必ず家族が、ならなければいけませんか?
8. 後見人選任の手続きは、どこに申し立てるのですか?
9. 後見人選任の申立ては、誰ができますか?
10. 後見人選任の申し立てには、どのくらい費用がかかりますか?
11. 後見人の選任には、どれくらいの期間がかかりますか?
12. 後見人になったら、どんな義務がありますか?
13. 後見人には、報酬を支払う必要がありますか?
14. 後見人は、家族の同意なしに契約できますか?
15. 後見人が不適切な行為をした場合は、どうなりますか?
16. 後見人の仕事は、どこまでが範囲ですか?
17. 後見人の報告義務とは、何ですか?
18. 後見監督人とは、何ですか?
19. 任意後見契約とは、具体的にどのような内容ですか?
20. 任意後見契約のメリットは、何ですか?
21. 任意後見契約は、いつから効力が発生しますか?
22. 任意後見監督人とは何ですか?
23. 任意後見契約を結んだ後、心変わりした場合はどうなりますか?
24. 任意後見制度と家族信託、どちらが良いですか?
25. 後見制度を利用しないと、どんなリスクがありますか?
26. 後見人になれない人は、いますか?
27. 後見制度は、一度利用したらやめられないのですか?
28. 後見制度と日常生活自立支援事業の違いは、何ですか?
29. 後見制度は、家族間の争いを避けるのに役立ちますか?
30. 後見制度を利用すると、本人の自由は奪われますか?
31. 後見人が選任されると、本人は契約ができなくなりますか?
32. 後見人制度を利用したいけど、親が嫌がっています。どうすればいいですか?
33. 後見人制度は、介護保険サービスとどう関係しますか?
34. 後見人制度と成年後見登記制度の、違いは何ですか?
35. 後見制度の申し立て前に、緊急で必要な手続きがある場合は?
36. 後見人の仕事は、誰かに任せられますか?
37. 後見制度を利用した場合、本人の財産は凍結されますか?
38. 後見人制度を利用したら、家族が財産を使えなくなりますか?
39. 後見制度を利用するタイミングは、いつが良いですか?
40. 後見制度の申し立てを、ためらってしまうのですが?
41. 後見人が決定したら、金融機関での手続きはどうなりますか?
42. 後見人制度と成年後見センターの関係は?
43. 市町村長による、後見開始の申立てとは?
44. 後見制度で、本人の遺言書作成はできますか?
45. 後見制度を利用中に、本人が亡くなったらどうなりますか?
46. 後見制度は、認知症予防になりますか?
47. 後見制度は、税金の申告もしてくれますか?
48. 後見人制度の利用を、途中でやめることはできますか?
49. 後見制度を利用するメリットはどんなことですか?
50. 後見制度について相談したいのですが, どこに連絡すればいいですか?