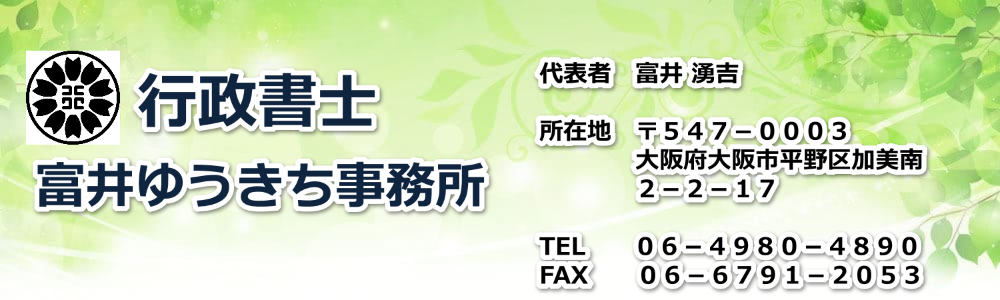相続の よくある質問ベスト50
1. 相続って
そもそも何ですか?
相続とは、
亡くなった方 ( 被相続人 ) の財産や権利義務を、
その方の配偶者や子どもなどの親族 ( 相続人 ) が引き継ぐことです。
財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれます。
相続は、
大切な方を失った悲しみの中で進めることが多く、
慣れない手続きに戸惑う方も少なくありません。
私たちは、そうしたお客様に寄り添い、
スムーズな手続きをサポートいたします。
2. 相続は
いつから始まりますか?
相続は、亡くなった方がお亡くなりになった日、
つまり 「 死亡した時 」 から開始されます。
相続人には、その日から様々な手続きや期限が始まるため、
早期に状況を把握し、
必要な対応を始めることが重要です。
特に、
相続放棄や限定承認には
3ヶ月という期限があるため、注意が必要です。
3. 相続人は
誰がなりますか?
相続人になれるのは、
法律で定められた順位の人が優先されます。
常に相続人となるのは配偶者です。
それ以外の親族は、
第一順位が子、
第二順位が父母、祖父母
第三順位が兄弟姉妹となります。
前の順位の人がいる場合は、
後ろの順位の人は相続人にはなれません。
4. 法定相続分って
何ですか?
法定相続分とは、
民法で定められた、
各相続人が相続できる財産の割合のことです。
例えば、
配偶者と子がいる場合は配偶者が2分の1、
子が2分の1(複数いる場合は
さらに均等に分割)となります。
遺言書がない場合や、
遺産分割協議がまとまらない場合の目安となりますが、
遺産分割協議で合意すれば、
この割合にとらわれずに分けることも可能です。
5. 相続財産には
何が含まれますか?
相続財産には、
現金、預貯金、不動産 ( 土地や建物 )、
有価証券 ( 株式など )、自動車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、
借金、住宅ローン、未払金などのマイナスの財産も含まれます。
これらを全て含めて 「 遺産 」 と呼び、
相続人はプラスもマイナスも引き継ぐことになります。
6. 相続財産に借金があった場合は
どうなりますか?
相続財産に借金が含まれる場合、
相続人はその借金も引き継ぐことになります。
もし借金の方が財産より多い場合は、
「 相続放棄 」 や 「 限定承認 」 という
手続きを検討することができます。
これらの手続きには期限があるため、
借金の有無や内容を早めに確認することが大切です。
7. 相続放棄とは
どんな手続きですか?
相続放棄とは、
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、
一切相続しないことです。
主に借金が多い場合に選択されます。
相続放棄をするには、
原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し立てる必要があります。
一度放棄すると撤回はできませんので、
慎重な判断が必要です。
8. 限定承認とは
何ですか?
限定承認とは、
相続した財産の範囲内で借金を返済し、
もし財産が残ればそれを相続するという手続きです。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合や
先祖代々の土地だけは残したいが借金があるかもしれない、
という場合に利用されることがあります。
相続人全員で申し立てる必要があり、
期限も相続放棄と同様に3ヶ月以内です。
9. 遺産分割協議って
何ですか?
遺産分割協議とは、
相続人全員で話し合い、
被相続人の財産をどのように分けるかを決めることです。
遺言書がない場合や、
遺言書があっても遺産分割協議が必要な場合に開催されます。
相続人全員の合意が必要で、
一人でも参加しなければ成立しません。
また、一人でも反対すれば、成立しません。
専門家が間に入ることで、円滑な協議をサポートできます。
10. 遺産分割協議書は
なぜ必要ですか?
遺産分割協議書は、
遺産分割協議で合意した内容を文書として、
明確に記録したものです。
この書類がないと、
不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、
相続税の申告などができません。
また、後々の相続トラブルを防ぐためにも、
法的な効力を持つ正式な書類として
作成することが非常に重要です。
11. 遺産分割協議がまとまらない場合は
どうなりますか?
遺産分割協議がまとまらない場合は、
まずは家庭裁判所に
「 遺産分割調停 」 を申し立てることができます。
調停委員が間に入って話し合いを促しますが、
それでも合意できない場合は 「 遺産分割審判 」 に移行し、
最終的に裁判所が財産の分け方を決定します。
裁判所は公正中立ですが、
平日の昼間に開催されますので負担が大きくなります。
長期化し、ご家族間の関係が悪化する可能性もあるため、
できるだけ話し合いでの解決を目指しましょう。
12. 相続税はいつまでに
誰が払うのですか?
相続税は、
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、
相続人が税務署に申告・納税する必要があります。
一般的には、死亡した日ですが、
遺贈された人などは、それを知った日になります。
相続財産の総額が
一定の基礎控除額を超える場合に課税されます。
期限を過ぎると延滞税などがかかるため、注意が必要です。
13. 相続税の基礎控除額って
何ですか?
相続税の基礎控除額とは、
相続財産の合計額がこの金額以下であれば
相続税がかからないという、非課税枠のことです。
計算式は 「 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 」 です。
例えば、法定相続人が3人なら、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円までは相続税がかかりません。
たとえ相続税がかからなくても、申告はしなければなりません。
この額を超える場合に相続税が発生します。
しかし、単純な計算では済まず
正確な申告には相続税に詳しい税理士に依頼することをおすすめします。
14. 相続税の申告は
自分でもできますか?
相続税の申告はご自身でも可能ですが
非常に複雑で専門知識が必要です。
税額の計算間違いや申告漏れがあると、
追徴課税や加算税が課されるリスクがあります。
正確な申告を行い、節税対策も考慮するのであれば、
相続税に詳しい税理士に依頼することをおすすめします。
15. 相続に必要な書類は
何ですか?
被相続人の死亡診断書、
戸籍謄本 ( 出生から死亡まで遡るもの )、
住民票の除票、
相続人全員の戸籍謄本、
住民票、
印鑑証明書、
財産に関する書類
( 預貯金通帳、不動産登記簿謄本、有価証券残高証明書など )、
借金に関する書類など
が一般的に必要です。
さらに、提出先によって、有効期間も様々です。
状況によってさらに多くの書類が求められることもあります。
16. 故人の預金は
勝手に引き出せますか?
故人名義の預貯金口座は、
死亡が金融機関に知らされるとすぐに凍結され、
原則として相続人であっても勝手に引き出すことはできません。
凍結を解除し、預貯金を引き出すためには、
遺産分割協議書や
相続人全員の印鑑証明書などの提出が必要です。
勝手に引き出すと、
後々トラブルの原因となる可能性もあります。
17. 葬儀費用は
相続財産から支払ってもいいですか?
葬儀費用は、
相続財産から支払うことが認められています。
ただし、
過度な費用は認められない場合がありますので注意が必要です。
葬儀費用を支払った場合は、
領収書をきちんと保管しておきましょう。
相続税の計算上、
一定の葬儀費用は控除の対象となることもあります。
18. 生命保険金は
相続財産になりますか?
生命保険金は、
原則として受取人固有の財産とされ、
相続財産には含まれません。
そのため、遺産分割協議の対象にはなりませんし、
相続放棄をしても受け取ることができます。
ただし、
相続税の計算においては、
「 みなし相続財産 」 として課税対象となる場合があります。
正確な申告を行い、節税対策も考慮するのであれば、
相続税に詳しい税理士に依頼することをおすすめします。
19. 死亡退職金は
相続財産になりますか?
死亡退職金も、
生命保険金と同様に、
原則として受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれません。
遺産分割協議の対象外ですが、
相続税の計算においては、
「 みなし相続財産 」 として課税対象となる場合があります。
正確な申告を行い、節税対策も考慮するのであれば、
相続税に詳しい税理士に依頼することをおすすめします。
20. 遺産の中に不動産がある場合
の注意点は?
不動産が遺産に含まれる場合、
名義変更 ( 相続登記 ) の手続きが必要です。
相続登記は義務化され、正当な理由なく放置すると
過料 ( かりょう ) の対象となる場合があります。
また、不動産の評価や、
共有名義にするか単独名義にするかなど、
相続人全員での合意形成が重要です。
売却や活用を検討する場合は、
さらに専門的な知識が必要になります。
21. 相続登記は
なぜ必要ですか?
相続登記とは、
被相続人名義の不動産を、
相続人名義に変更する手続きのことです。
この登記をしていないと、
不動産の売買や担保設定ができません。
また、
誰が真の所有者か外部から判断できないため、
将来的なトラブルの原因となる可能性があります。
2024年4月1日からは相続登記が義務化されました。
22. 相続登記の義務化とは
何ですか?
2024年4月1日から、
相続による不動産取得を知った日から3年以内に、
相続登記をすることが義務化されました。
正当な理由なく怠ると、
10万円以下の過料 ( かりょう ) が科される可能性があります。
これにより、
所有者不明土地問題の解消や、
不動産取引の安全確保が目的とされています。
23. 相続した不動産を
売却したいのですが?
相続した不動産を売却するためには、
まず相続登記を完了させ、
売却する相続人の名義にする必要があります。
その後、不動産業者に依頼して売却活動を進めます。
売却益が出た場合には、
譲渡所得税が課税される可能性があり、
特例が適用できる場合もありますので、
税理士に相談することをおすすめします。
24. 相続した空き家を
どうすればいいですか?
相続した空き家は、
固定資産税や管理費用がかかり、
放置すると老朽化や近隣トラブルの原因になることもあります。
売却、賃貸、リフォームして活用、あるいは解体して更地にするなど、
様々な選択肢があります。
私たちは、お客様のご状況に合わせて、
最適な空き家対策を一緒に考え、
専門家と連携しながらサポートいたします。
25. 遺言書が見つかったら
どうすればいいですか?
遺言書が見つかったら、
まずその種類を確認しましょう。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、
開封せずに家庭裁判所で 「 検認 」 の手続きを行う必要があります。
公正証書遺言の場合は、検認は不要です。
勝手に開封したり、内容を改ざんしたりすると、
法的な罰則の対象となる可能性がありますので注意が必要です。
26. 遺言書がない場合
親族関係が複雑だとどうなりますか?
遺言書がなく、
親族関係が複雑な場合( 例えば、養子縁組、再婚した方 )、
内縁関係の方がいた場合、
連絡が取れない相続人がいる場合などは、
相続人調査や遺産分割協議が非常に困難になることがあります。
相続人全員の同意が必要となるため、
話し合いが進まず、調停や審判に移行する可能性が高まります。
早期に専門家に相談し、
適切なアドバイスを受けることが重要です。
27. 相続人の中に未成年者がいる場合は
どうなりますか?
相続人の中に未成年者がいる場合は、
その未成年者は遺産分割協議に参加できません。
未成年者の代わりに 「 特別代理人 」 を、
家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
親権者が他の相続人でもある場合 ( 利益相反関係 ) も、
特別代理人が必要になります。
手続きが複雑になるため、
専門家に相談することをおすすめします。
28. 相続人の中に認知症の人がいる場合は
どうなりますか?
相続人の中に認知症などで
判断能力が低下している方がいる場合は、
その方は遺産分割協議に参加できません。
この場合、「 成年後見制度 」 を利用し、
家庭裁判所に後見人を選任してもらう必要があります。
後見人が、
ご本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。
29. 遺産分割協議は
いつまでにしなければなりませんか?
遺産分割協議に、法的な期限はありません。
しかし、
相続税の申告・納税には10ヶ月以内という期限があり、
不動産の名義変更 ( 相続登記 ) も
3年以内という義務化が始まりました。
これらの手続きには遺産分割協議書が必要となるため、
実質的には早期の合意が求められます。
30. 故人の債務を
相続人が知らなかった場合は?
相続開始から3ヶ月を過ぎてから、
被相続人に借金があったことを知った場合でも、
例外的に相続放棄が認められるケースがあります。
しかし、
非常に限定的な場合であり、裁判所の判断によります。
借金がある可能性が少しでもある場合は、
安易に相続を承認せず、
専門家に相談することが重要です。
31. 連絡が取れない相続人がいる場合は
どうなりますか?
連絡が取れない相続人がいる場合でも、
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
まずは戸籍調査で所在を確認し、手紙などで連絡を試みます。
それでも連絡が取れない場合は、
家庭裁判所に 「 不在者財産管理人 」 の選任を、
申し立てるなどの手続きが必要になります。
非常に複雑なケースとなるため、
専門家への相談が不可欠です。
32. 遺産分割の話し合いで
感情的になってしまうのですが?
相続は、
故人を偲ぶ大切な時期でもあり、
感情的になりやすいものです。
特に、金銭が絡む話し合いでは、
感情的な対立が生じやすくなります。
このような場合、
私たち行政書士のような第三者が間に入ることで、
冷静な話し合いを促し、
感情的なもつれを避けながら円満な解決へ導くことができます。
33. 相続人の間で揉めていますが
どこに相談すればいいですか?
相続人同士でトラブルが起きている場合は、
弁護士にご相談いただくのが最も適切です。
弁護士は、法律の専門家として、お客様の代理人となり、
交渉や調停・審判の手続きを進めることができます。
私たちは、弁護士と連携しながら、
手続きをサポートすることも可能です。
34. 寄与分 ( きよぶん ) とは
何ですか?
寄与分とは、
共同相続人の中に、
被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した人がいた場合に、
その貢献度に応じて、
通常の法定相続分より多くの財産を受け取れるという制度です。
例えば
、
被相続人の事業を手伝ったり、
介護をしたりした場合などが該当します。
35. 特別受益 ( とくべつじゅえき ) とは
何ですか?
特別受益とは、
共同相続人の一部が、
被相続人から生前に特別に受けた贈与や遺贈のことです。
例えば、
不動産をもらっていたり、
大学の学費を通常の範囲を超えて援助してもらっていたりするケースです。
これは遺産分割の際に、
相続分を計算する際に考慮されることがあります。
36. 遺留分侵害額請求とは
何ですか?
遺留分侵害額請求とは、
遺言書の内容によって、
兄弟姉妹以外の法定相続人が法律で保障されている
最低限の相続分 ( 遺留分 ) を侵害された場合に、
その侵害された分を取り戻すために請求できる権利のことです。
裁判所に訴えてから、判決をもらいます。
この請求には時効があるため、注意が必要です。
37. 相続税の節税対策は
できますか?
相続税の節税対策には、
生前贈与の活用、
生命保険の非課税枠の利用、
不動産の有効活用、
養子縁組など、
様々な方法があります。
しかし、対策は早ければ早いほど効果的で、
専門的な知識も必要です。
税理士と連携しながら、
お客様の状況に合わせた最適な節税対策をご提案します。
38. 準確定申告とは
何ですか?
準確定申告とは、
亡くなった方 ( 被相続人 ) が
亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について行う、
所得税の確定申告のことです。
被相続人の代わりに相続人が行う必要があり、
原則として死亡を知った日の翌日から
4ヶ月以内に行う必要があります。
39. 財産の名義変更は
自分でもできますか?
預貯金や株式などの名義変更は、
比較的ご自身でも可能ですが、
金融機関ごとに手続きが異なります。
不動産の名義変更 ( 相続登記 ) は専門的な知識が必要で、
司法書士に依頼するのが一般的です。
複雑な手続きを確実に進めるためには、
専門家への依頼を検討することをおすすめします。
40. 遺産に海外の財産がある場合は
どうなりますか?
遺産に海外の財産が含まれる場合は、
その国の法律が適用される場合があるため、
非常に複雑になります。
相続税も、
日本と海外の両方で課税される可能性があります ( 国際相続 )。
専門知識と国際的な連携が必要となるため、
国際相続に強い弁護士や税理士、
行政書士にご相談いただくのが賢明です。
41. 相続財産の評価は
どうやって行いますか?
不動産は固定資産税評価額や路線価などを基に、
預貯金は残高証明書、
有価証券は死亡日の終値、
などを基に評価します。
非上場株式など、
評価が難しい財産もあります。
相続税の申告においては、
財産評価が税額に大きく影響するため、
専門家(税理士など)による正確な評価が不可欠です。
42. 相続人全員が海外にいる場合は
どうなりますか?
相続人全員が海外にいる場合でも、
日本の法律に基づいて相続手続きを進める必要があります。
書類の郵送や、
海外在住の相続人のサイン ( 署名 ) や
印鑑証明書の代わりに現地の公証役場で認証を受けるなど、
通常より手続きが複雑になります。
オンラインでの相談や、
国際相続に詳しい専門家への依頼が有効です。
43. 遺品整理は
いつ行えばいいですか?
遺品整理は、
相続財産の全体像を把握するためにも、
できれば相続手続きが落ち着いてから行うのが理想的です。
特に、
価値のあるものや故人の大切な書類が紛れていないか、
慎重に確認する必要があります。
感情的になりやすい作業でもあるため、
無理せず、
専門の遺品整理業者に依頼することも検討しましょう。
44. 相続放棄の後に
故人の借金が見つかった場合は?
相続放棄の申述 ( しんじゅつ ) が
家庭裁判所で受理された後であれば、
原則として故人の借金を支払う義務はありません。
しかし、
もし相続放棄が受理される前に、
相続財産を処分してしまったりすると、
相続を承認したとみなされ、
放棄が認められなくなる可能性があります。
不明な点があれば、すぐに弁護士に相談しましょう。
45. 相続手続きで困ったら
どこに相談すればいいですか?
相続手続きは、
その内容によって相談先が異なります。
遺言書作成や相続人調査、遺産分割協議書の作成などは行政書士、
相続税申告は税理士、
不動産の名義変更は司法書士、
相続人同士の紛争解決は弁護士
が専門です。
当事務所では、お客様のお悩みに合わせて、
適切な専門家と連携しながら、総合的にサポートいたします。
46. 相続に関する
無料相談はありますか?
はい、あります。
多くの行政書士事務所や弁護士事務所、税理士事務所などで、
初回無料相談を実施しています。
まずは無料相談を活用して、ご自身の状況を説明し、
専門家からアドバイスを受けることをおすすめします。
複数の事務所で相談することで、
ご自身に合った専門家を見つけやすくなります。
47. 相続税の申告期限に間に合わない場合は
どうなりますか?
相続税の申告期限である10ヶ月に間に合わない場合は、
延滞税が課されたり、
配偶者控除などの特例が適用できなくなったりする可能性があります。
期限に間に合わないことが確実な場合は、早めに税理士に相談し、
適切な対応を検討しましょう。
無申告加算税や重加算税が課される場合もあります。
48. 相続人に行方不明者がいる場合は
どうなりますか?
相続人の中に行方不明者がいる場合でも、
その人を除いて遺産分割協議を進めることはできません。
家庭裁判所に 「 不在者財産管理人 」 の選任を申し立て、
その管理人を介して遺産分割協議を進めることになります。
手続きに時間がかかるため、
早期の対応が必要です。
49. 相続手続きに費用は
どのくらいかかりますか?
相続手続きにかかる費用は、
財産の規模、手続きの複雑さ、
依頼する専門家によって大きく異なります。
相続税、登記費用、
弁護士や行政書士への報酬などが主な費用です。
無料相談などを利用して、
事前に見積もりを取ることをおすすめします。
50. 生前贈与と相続は
どちらが得ですか?
生前贈与と相続では、
それぞれ税金の種類や
税率、控除の仕組みが異なります。
一概にどちらが得とは言えませんが、
将来の相続税を考慮した上で、
計画的に生前贈与を行うことで、
税負担を軽減できる場合があります。
相続税に詳しい税理士と相談し、
お客様の状況に合わせた
最適なプランを立てることが重要です。