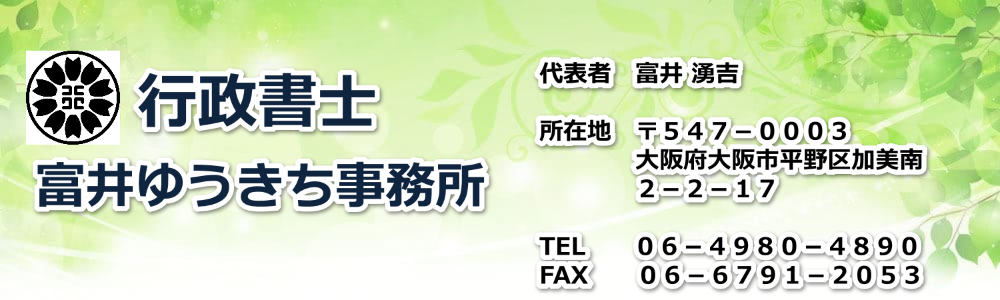遺産分割協議書 よくある質問ベスト50
1. Q. 遺産分割協議書はなぜ必要ですか?
A. 遺産分割協議書は、
相続人全員で合意した遺産の分け方を
明確にするための重要な書類です。
不動産の名義変更や預貯金の解約など、
相続手続きの多くで提出が求められます。
トラブル防止のためにも不可欠です 。 ?
2. Q. 遺産分割協議書がなくても
相続手続きはできますか?
A. 遺産分割協議書がなくても進められる手続きもありますが、
不動産の名義変更や銀行口座の解約など、
多くの手続きで必要となります。
特に相続人が複数いる場合、
トラブル防止のためにも作成を強く推奨します 。 ?
3. Q. 遺産分割協議書の作成には、
どのような書類が必要ですか?
A. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、
相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、
相続財産に関する書類(不動産登記簿謄本、
預貯金残高証明書など)が必要です。
これらの書類収集も当事務所でサポート可能です 。
?
4. Q. 相続人調査とは何ですか?
なぜ必要ですか?
A. 相続人調査とは、
故人の出生から死亡までの戸籍を辿り、
法的に相続人となる方を全て特定する手続きです。
想定外の相続人が見つかることもあり、
後々のトラブルを防ぎ、
遺産分割協議を有効に進めるために不可欠です 。 ?
5. Q. 財産調査はなぜ必要ですか?
自分でできますか?
A. 故人のプラス・マイナス全ての財産を明らかにし、
遺産分割協議や相続税申告の基礎とするために必要です。
ご自身でも可能ですが、
複雑な場合や漏れを防ぐためには
専門家への依頼が安心です 。 ?
6. Q. 遺産分割協議書作成を
行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A. 行政書士に依頼するメリットは、
法的に有効な書類を正確に作成できる点です。
複雑な相続関係や財産の種類に対応し、
記載漏れや不備による将来のトラブルを防ぎます。
また、相続人調査や財産調査もサポートし、
お客様の負担を大幅に軽減します 。 ?
7. Q. 遺産分割協議がまとまらない場合、
どうすれば良いですか?
A. 相続人全員の合意が得られない場合、
遺産分割協議は成立しません。
まずは話し合いを継続することが重要ですが、
それでも解決しない場合は、
家庭裁判所の調停や審判といった
法的手続きを検討することになります 。 ?
8. Q. 遺産分割協議書に記載すべき
内容は決まっていますか?
A. 被相続人の情報、
相続人全員の情報、
相続財産の種類と具体的な分け方、
そして相続人全員が合意した旨を明記し、
署名・押印(実印)が必要です。
特に不動産など登記が必要な財産は、
正確な表示が求められます 。
?
9. Q. 遺産分割協議書に
印鑑証明書は必要ですか?
A. はい、遺産分割協議書には相続人全員の実印での押印と、
その印鑑が本物であることを証明する印鑑証明書が必要です。
これは、
協議の正当性と有効性を担保するために非常に重要です 。 ?
10. Q. 遺産分割協議書は、
いつまでに作成すれば良いですか?
A. 法的な作成期限はありませんが、
相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)や、
不動産の名義変更の義務化(2024年4月1日施行)などを考慮すると、
速やかな作成が推奨されます。
早めの作成で、
後の手続きをスムーズに進められます。
11. Q. 遺産分割協議書は、
公正証書にする必要がありますか?
A. 必ずしも公正証書にする必要はありません。
相続人全員の実印と印鑑証明書があれば法的に有効です。
しかし、公正証書にすることで、
紛失や偽造のリスクを減らし、
より高い証明力を持つことができます。
当事務所は、公正証書作成のサポートも可能です。
12. Q. 遺産分割協議書に記載漏れがあった場合、
どうなりますか?
A. 記載漏れがあった場合、
その部分については再度相続人全員で協議し、
追加の協議書を作成する必要があります。
記載漏れがあると、後々の手続きで問題が生じたり、
新たなトラブルの原因となる可能性があります。
当事務所が正確な書類作成を徹底します。
13. Q. 遺産分割協議書は、
パソコンで作成しても有効ですか?
A. はい、遺産分割協議書はパソコンで作成しても有効です。
ただし、
相続人全員の署名(自筆)と実印での押印は必須です。
内容に不備がないよう、
法的な要件を満たしているか専門家が確認することをお勧めします。
14. Q. 遺産分割協議書に署名・押印を
拒否する相続人がいる場合は?
A. 遺産分割協議書への署名・押印を拒否する相続人がいる場合、
協議は成立しません。
まずは、その理由を丁寧に聞き、
話し合いを続けることが重要です。
それでも解決しない場合は、
家庭裁判所の調停や審判を検討することになります 。
?
15. Q. 遺産分割協議書は、
誰が保管するのですか?
A. 通常、相続人の代表者が原本を保管し、
他の相続人は写しを保管します。
不動産登記や預貯金解約など、
手続きの際に原本の提出を求められることが多いため、
大切に保管する必要があります。
16. Q. 遺産分割協議書作成の前に、
相続放棄を検討すべきケースはありますか?
A. 故人に多額の借金や負債があることが判明した場合、
相続放棄を検討すべきです。
相続放棄には期限(相続開始を知ってから3ヶ月以内)があるため、
財産調査と並行して速やかに判断する必要があります 。 ?
17. Q. 遺産分割協議書作成を行政書士に
依頼した場合の報酬の目安は?
A. 行政書士に遺産分割協議書作成を依頼した場合の報酬は、
事案の複雑さや財産の種類、
相続人の数などによって異なりますが、
一般的には10万円?40万円が目安とされています 。 ?
18. Q. 遺産分割協議書作成後、
預貯金の解約や自動車の名義変更も依頼できますか?
A. はい、遺産分割協議書作成後、
その内容に基づいた預貯金の解約手続きや自動車の名義変更手続きも、
行政書士の業務範囲として代行可能です。
お客様が煩雑な手続きに追われることなく、
スムーズに相続を完了できるようサポートいたします 。 ?
19. Q. 遺産分割協議書に、
相続人全員が署名・押印できない場合は?
A. 相続人全員が署名・押印できない場合、
遺産分割協議書は無効となります。
例えば、海外在住や病気などで直接署名できない場合は、
委任状を用いて代理人が手続きを行うことも可能です。
当事務所は、個別の状況に応じた対応策をアドバイスいたします。
20. Q. 遺産分割協議書に、
相続財産以外のことも記載できますか?
A. 原則として相続財産の分割について記載するものですが、
相続人全員の合意があれば、
付随的な事項(例:葬儀費用の分担、遺品整理についてなど)を
記載することも可能です。
ただし、法的な効力を持たない場合もありますので注意が必要です。
21. Q. 遺産分割協議書は、
相続税の申告に影響しますか?
A. はい、
遺産分割協議書は相続税の申告に大きく影響します。
誰がどの財産を相続したかによって、
相続税の計算や特例の適用が変わるため、
正確な協議書が必要です。
当事務所は税理士と連携し、
スムーズな手続きをサポートします 。 ?
22. Q. 遺産分割協議書作成の際、
行政書士は法律相談に乗ってくれますか?
A. 行政書士は、
相続全般に関する一般的な法律や制度の説明はできますが、
具体的な遺産分割の内容に関する個別的な法律相談は
弁護士の独占業務であり、行うことはできません。
当事務所は、
書類作成や手続き代行を通じてお客様をサポートします 。
?
23. Q. 遺産分割協議書に、
遺言書の内容と異なる合意を記載しても有効ですか?
A. 遺言書がある場合でも、
相続人全員が合意すれば、
遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことは可能です。
その合意内容を
遺産分割協議書に記載することで有効となります。
ただし、一人でも遺言通りの分割を希望する相続人がいれば、
遺言が優先されます 。 ?
24. Q. 遺産分割協議書作成後、
不動産の名義変更(相続登記)も依頼できますか?
A. 不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務であり、
行政書士は直接行うことができません。
しかし、当事務所は提携の司法書士と連携し、
遺産分割協議書作成から相続登記まで、
一貫したサポート体制を整えております 。 ?
25. Q. 遺産分割協議書作成の相談は、
オンラインでも可能ですか?
A. はい、
当事務所ではオンラインでのご相談も承っております。
遠方にお住まいの方や、ご来所が難しい方でも、
ご自宅から安心してご相談いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
26. Q. 相続財産に不動産が含まれる場合、
遺産分割協議書にはどう記載しますか?
A. 不動産を記載する際は、
登記簿謄本に記載されている通りに、
所在地、地番、地目、地積(土地)、家屋番号、種類、構造、床面積(建物)などを
正確に記載する必要があります。
当事務所が正確な記載をサポートします 。
?
27. Q. 遺産分割協議書作成の際、
相続人全員が揃う必要はありますか?
A. 遺産分割協議書は
相続人全員の合意に基づいて作成されるため、
原則として全員が協議に参加し、
署名・押印する必要があります。
ただし、委任状による代理参加も可能です。
28. Q. 遺産分割協議書作成の際、
行政書士はどのような調査をしてくれますか?
A. 相続人調査(戸籍収集による相続人の特定)や
財産調査(預貯金、不動産、借金などの特定)を行います。
これらの調査は、
正確な遺産分割協議書作成の基礎となります 。 ?
29. Q. 遺産分割協議書作成の際、
遺言書が見つかったらどうなりますか?
A. 遺言書がある場合、
原則として遺言書の内容が優先されます。
ただし、相続人全員の合意があれば、
遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことも可能です 。 ?
30. Q. 遺産分割協議書作成後、
トラブルになった場合、行政書士は対応してくれますか?
A. 行政書士は、
紛争性の高い案件の代理人となることはできません。
もしトラブルが法的な紛争に発展した場合は、
弁護士をご紹介するなど、
適切な専門家との連携をサポートいたします 。 ?
31. Q. 遺産分割協議書に、
代償分割を記載することはできますか?
A. はい、代償分割(特定の相続人が遺産を多く取得する代わりに、
他の相続人に金銭を支払う方法)を
遺産分割協議書に記載することは可能です。
その際は、
代償金の金額や支払い方法を明確に記載します。
32. Q. 遺産分割協議書作成の際、
相続財産に海外の資産が含まれる場合は?
A. 海外の資産が含まれる場合、
その国の法律や手続きも考慮する必要があります。
当事務所は、
国際相続に関する一般的な情報提供や、
必要に応じて専門家との連携をサポートいたします 。
?
33. Q. 遺産分割協議書作成の相談は、
秘密厳守で対応してもらえますか?
A. はい、行政書士には守秘義務がありますので、
ご相談内容は厳重に管理され、
外部に漏れることは一切ありません。
安心してご相談ください。
34. Q. 遺産分割協議書作成を依頼した場合、
契約前に見積もりはもらえますか?
A. はい、当事務所では、
ご依頼いただく前に必ず詳細な見積もりをご提示し、
ご納得いただいてから契約を進めます。
費用の透明性を大切にしています 。 ?
35. Q. 遺産分割協議書作成の際、
相続人の一人が行方不明の場合は?
A. 行方不明の相続人がいる場合、
家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行うなどの
手続きが必要になります。
当事務所は、
このような複雑な状況での手続きもサポートいたします。
36. Q. 遺産分割協議書に、
寄与分や特別受益を反映させることはできますか?
A. はい、相続人全員の合意があれば、
寄与分(故人の財産維持・増加に貢献した分)や
特別受益(生前に故人から受けた特別な利益)を
考慮した遺産分割協議書を作成できます。
37. Q. 遺産分割協議書作成の際、
相続税の節税対策についても相談できますか?
A. 行政書士は相続税の
具体的な節税対策に関するアドバイスはできませんが、
税理士と連携し、
相続税の負担を軽減するための
遺産分割方法について情報提供を行うことは可能です 。 ?
38. Q. 遺産分割協議書作成の際、
相続人に未成年者がいる場合はどうなりますか?
A. 未成年者が相続人にいる場合、
その未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人は、
家庭裁判所に申立てて選任されます。
当事務所が手続きをサポートします 。 ?
39. Q. 遺産分割協議書作成の際、
遺産に不動産しかない場合はどうなりますか?
A. 遺産が不動産のみの場合、
共有名義にするか、
特定の相続人が取得して他の相続人に
代償金を支払うなどの方法があります。
将来のトラブルを避けるため、慎重な検討が必要です 。 ?
40. Q. 遺産分割協議書作成の際、
葬儀費用は相続財産から清算できますか?
A. 葬儀費用は、
相続財産から清算することが可能です。
遺産分割協議書にその旨を記載し、
相続人全員で合意することで、
後々のトラブルを防ぐことができます 。 ?
41. Q. 遺産分割協議書作成の際、
行政書士はどのような流れで業務を進めますか?
A. まずは初回相談で状況を伺い、
相続人調査、財産調査を行います。
その後、遺産分割協議書の原案を作成し、
相続人全員の合意形成をサポート。
最終的に署名・押印をいただき、
完成となります 。 ?
42. Q. 遺産分割協議書作成の際、
相続財産に生命保険金は含まれますか?
A. 生命保険金は、
受取人が指定されている場合、
原則として受取人固有の財産となり、
遺産分割協議の対象とはなりません。
ただし、
例外的に遺産分割の対象となるケースもあります 。 ?
43. Q. 遺産分割協議書作成の際、
遺言執行者がいる場合はどうなりますか?
A. 遺言執行者がいる場合、
その遺言執行者が遺言の内容に従って遺産分割を進めます。
遺言執行者がいる場合でも、
相続人全員の合意があれば
遺言と異なる遺産分割協議を行うことは可能です。
44. Q. 遺産分割協議書作成の際、
相続税の申告期限に間に合わない場合は?
A. 相続税の申告期限(10ヶ月)までに
遺産分割協議がまとまらない場合でも、
一旦法定相続分で申告・納税し、
後から遺産分割協議書が完成次第、
修正申告を行うことが可能です。
45. Q. 遺産分割協議書作成の際、
相続財産に株式や有価証券が含まれる場合は?
A. 株式や有価証券も相続財産に含まれます。
遺産分割協議書には、
銘柄、数量、評価額などを正確に記載する必要があります。
評価方法についてもアドバイス可能です 。 ?
46. Q. 遺産分割協議書作成の際、
相続人が行方不明で連絡が取れない場合は?
A. 行方不明の相続人がいる場合、
家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行うなどの
手続きが必要になります。
当事務所は、
このような複雑な状況での手続きもサポートいたします。
47. Q. 遺産分割協議書作成の際、
相続財産に自動車が含まれる場合は?
A. 自動車も相続財産に含まれます。
遺産分割協議書には、車種、登録番号などを記載し、
名義変更の手続きが必要になります。
名義変更手続きも当事務所で代行可能です 。 ?
48. Q. 遺産分割協議書作成の際、
相続財産にゴルフ会員権やリゾート会員権が含まれる場合は?
A. ゴルフ会員権やリゾート会員権も
相続財産に含まれる場合があります。
その評価方法や名義変更手続きは複雑な場合があるため、
専門家にご相談いただくことをお勧めします。
49. Q. 遺産分割協議書作成の際、
相続財産に著作権や特許権が含まれる場合は?
A. 著作権や特許権などの無形財産も
相続の対象となる場合があります。
その評価や承継方法については専門的な知識が必要となるため、
当事務所にご相談ください。
50. Q. 遺産分割協議書作成の際、
相続財産に骨董品や美術品が含まれる場合は?
A. 骨董品や美術品も相続財産に含まれます。
その評価は専門家による鑑定が必要となる場合があります。
遺産分割協議書には、その品名や評価額を記載します。