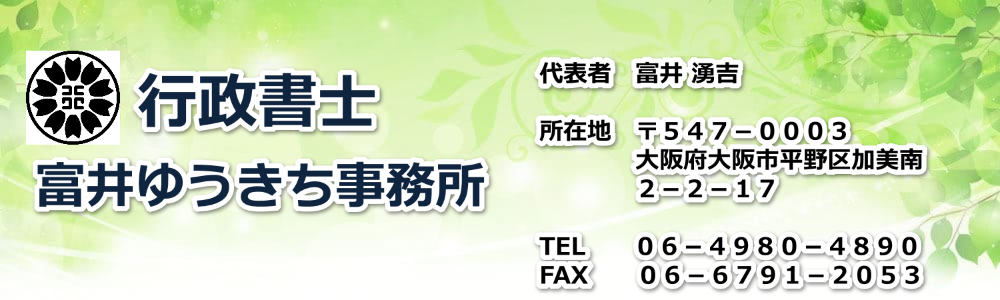�⌾���́@�悭���鎿��x�X�g�T�O
1. �⌾�����āA���̂��߂ɍ����̂ł����H
�⌾���́A
���Ȃ����S���Ȃ�����Ɋ��܂��B
�u �c���ꂽ���Y��N�ɂǂ̂悤�ɕ��������� �v
�u ���Ƒ��ւ̃��b�Z�[�W�⊴�ӂ̋C���� �v
�Ȃǂm�ɓ`���邽�߂́A�@�I�ȏ��ނȂ̂ł��B
�@����ɂ��A
�������߂��邲�Ƒ��Ԃ̑�����h���܂��B
�@����ɁA
�X���[�Y�ȑ����葱���𑣂����Ƃ��ł��܂���B�@
�@���Ȃ��� �u �Ō�̈ӎv �v �d���A
���Ƒ������S���Ė�������߂�悤�ɂ��邽�߂ł��B
���Ȃ��ɂ����ł��Ȃ��A
��ȏ����ƌ�����ł��傤�ˁB
2. �⌾�����Ȃ��ƁA�ǂ��Ȃ�܂����H
�@�⌾�����Ȃ��ꍇ�́A
�@���Œ�߂�ꂽ�����l�S����
�u ��Y�������c �i������Ԃ��傤���j�v ���s���A
�b�������ō��Y�̕����������߂邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�������A�S���̍��ӂ������Ȃ��ƁA
��Y��������A
�ň��̏ꍇ�͉ƒ�ٔ����ł̒���i���傤�Ă��j��R���i����ς�j�ɔ��W���A
���Ƒ��Ԃ̊W���������Ă��܂��\��������܂��B
�@���̂悤�ɁA�⌾�����Ȃ����Ƃ́A
���Ƒ��ɑ傫�ȕ��S��A
�g���u���������N�������X�N������̂ł��B
3. �⌾��������A�K�������͋N���܂��H
�@�⌾��������A
�����Ɋւ��邠�Ȃ��̈ӎv�����m�ɂȂ邽�߁A
�����̑����g���u���𖢑R�ɖh�����Ƃ��ł��܂��B
�@�������A
�⌾�̓��e�����Ă�����A
����̑����l�Ɉ◯�� �i ����イ�Ԃ� �j ��N�Q����悤�ȓ��e�������肷��ƁA
�g���u���ɂȂ�\��������܂��B
�@���ƂƑ��k���Ȃ���A�@�I�ɗL���ŁA
���A���Ƒ��ɔz���������e�ɂ��邱�Ƃ���ł��ˁB
4. �ǂ�Ȑl���A�⌾�������ׂ��ł����H
�@���Y��������A
���Ƒ��̏����G�ȕ� �i �č��A�����W�A�q�����Ȃ��v�w�Ȃ� �j�A
����̍��Y�����̐l�ɓn���������A
���b�ɂȂ����l�ɍ��Y���������A
���P�c�̂Ɋ�t���������ȂǁA
�����̕��Ɉ⌾���쐬���������߂��܂��B
�@���ɁA
�@�u ���ߎ���������� �v
�@�u �Ƒ��ɕ��S�����������Ȃ� �v
�ƍl������́A���߂ɍ쐬���������܂��傤�B
5. �⌾���̎�ނɂ́A�ǂ�Ȃ��̂�����܂����H
�⌾���ɂ͎��
�@ �u ���M�؏��⌾ �v �i ���Ђ��傤����⌾ �j
�A �u �����؏��⌾ �v �i �����������傤����⌾ �j
�B �u �閧�؏��⌾ �v �i �Ђ݂��傤����⌾ �j
��3��ނ�����܂��B
�@���ꂼ��쐬���@��ۊǕ��@�A
�@�I�Ȍ��͂Ȃǂɓ���������܂��B
�@�����g�̏��]�ɍ��킹�āA
�ǂ̎�ނ̈⌾�����œK����I�Ԃ��Ƃ��d�v�ł��ˁB
�@�܂��A1��ނ����łȂ��A
�����̈⌾����g�ݍ��킹����@������܂���B
�@���ꂼ��̓����𗝉����A
�����g�ɓK�������@�ō쐬���܂��傤�B
6. ���M�؏��⌾�Ƃ́A�ǂ�Ȃ��̂ł����H
���M�؏��⌾�́A
�⌾�Ҏ��g���A
�u �S�� �v�A�u ���t �v�A�u ���� �v ��S�Ď菑�����A
�u ���� �v ���邱�Ƃō쐬����⌾���ł��B
�@��p�������炸��y�ɍ쐬�ł���_�������b�g�ł��ˁB
�@�������A
�`���ɕs��������Ɩ����ɂȂ�����A
�����E�U���̃��X�N���������肵�܂���B
�@�܂��A
�ƒ�ٔ����ł�
�u ���F �i����ɂ�j�v �Ƃ����葱�����A�K�v�ɂȂ�܂��B
7. ���M�؏��⌾���A�쐬����ۂ̒��ӓ_�́H
���M�؏��⌾�́A
�S�����A�⌾�Ҏ��g���A
�����Ƃ��Ď菑������K�v������܂��B
�@�p�\�R���ō쐬������A
���l����M�����肵�������͖����ɂȂ�܂��ˁB
�@���t�Ǝ����A��������߂�ꂽ�����ŁA�K���L�ڂ��܂��B
�@�Ⴆ�A �w �ꌎ�g�� �x �͂����܂��ŁA
�m���ȓ��t�Ƃ͔F�߂��܂���B
�@���e�������܂����Ɖ��߂������ꂽ��A
���Y������ł��Ȃ������肷��\��������܂��B
�`���s���Ŗ����ɂȂ�Ȃ��悤�A�אS�̒��ӂ��K�v�ł��B
8. �����؏��⌾�Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂ł����H
�@�����؏��⌾�́A
���ؖ��� �i �������傤�₭�� �j �Ō��ؐl �i �������傤�ɂ� �j ���A
�⌾�҂̘b�����A�쐬����⌾���ł��B
�@�ؐl �i ���傤�ɂ� �j �Q�l�ȏ�̗�������K�v�ł��B
�@�@���̐��Ƃ��֗^���邽�߁A
�@�I�ȕs�����Ȃ��A�ł��m�����̍����⌾���ƌ����܂��ˁB
�@���{�͌��ؖ���ŕۊǂ���邽�߁A
������U���̐S�z������܂���B
�@����ɁA
�ƒ�ٔ����ł̌��F �i ����ɂ� �j�葱 ���A�s�v�ł���B
9. �����؏��⌾�́A�����b�g�͉��ł����H
���ؐl���֗^���邽�߁A
�@�I�ɗL���Ȉ⌾�����쐬�ł��܂��B
�@��X�̃g���u����h���₷���_���A�ő�̃����b�g�ł��ˁB
�@���{�����ؖ���ɕۊǂ���邽�߁A
������U���̐S�z������܂���B
�@�܂��A
���F�葱�����s�v�Ȃ��߁A
�����J�n��̎葱�����X���[�Y�ɐi�݂܂���B
�@�����g�̈ӎv���m���Ɏ��������A
���S��������܂��ˁB
10. �閧�؏��⌾�Ƃ́A�ǂ�Ȃ��̂ł����H
�@�閧�؏��⌾�́A
�⌾���̓��e��N�ɂ��m��ꂸ�ɁA
�쐬�ł���⌾���ł��B
�@�⌾�Ҏ��g���쐬�����⌾�����ɓ���A�@
���ؐl�Əؐl�̑O�ł��̕����ɉ��A
���ؐl�������ɓ��t�⎁�����L�ڂ��܂��B
�@���e�̔閧���ۂ����_���A�����ł��ˁB
�@�������A
���e�̗L�����܂ł͌��ؐl���m�F���Ȃ����߁A
�`���s���̃��X�N������܂���B
�܂��A�ٔ����ł̌��F�葱�����K�v�ł��ˁB
11. �⌾���ɁA��������e�͉��ł����H
�@�⌾���ɂ́A
���Y�̕����� �i �②�A�������̎w��Ȃ� �j �����łȂ��A
�F�m�i �ɂ� �j�A
���葊���l�̔p���i �͂����� �j�A
�⌾���s�҂̎w��A
���J �i ����A�@�v �j ��Ɏ҂̎w��A
�q�ւ̃��b�Z�[�W�A
�⍜�̊�]�ȂǁA
�l�X�Ȃ��Ƃ��������Ƃ��ł��܂���B
�@�������A
�@�I�Ȍ��͂��������ƁA
�P�Ȃ�t������ �i �ӂ������E���肢��b�Z�[�W �j ���A
��ʂ��ċL�q����K�v������܂��ˁB
�@�Ȃ��A�ǂ�����ɋL�ڂ���̂��́A
�{�l�̎��R�ł���B
12. ���Y�����Ȃ��Ă��A�⌾���͕K�v�ł����H
�@�P�T���珑����ƌ������Ƃ́A
�⌾�͍��Y��������Ȃ��̂ł���B
�@���Y�̑������Ȃ��ɂ�����炸�A
�⌾���͖��ɗ����܂��ˁB
�@�Ⴆ�A
���z�ł��s���Y������ꍇ��A
����̋L�O�i�����̉Ƒ��ɓn�������ꍇ�Ȃǂł��B
�@�⌾�������邱�ƂʼnƑ��Ԃ̃g���u���𖢑R�ɖh���A
���Ȃ��̈ӎv�m�ɓ`�����܂��B
�@��s�a�������łȂ��A
���Ɨp�ԁA�g�ѓd�b�̏����ɂ��K�v�ɂȂ�܂��B
�@���Y�����Ȃ����炱���A
�������ɂ��Ė��m�ɂ��Ă������Ƃ���ɂȂ�ꍇ������܂���B
���Ȃ��Ă��A�Ƒ��ɔ[�����Ă��炤���Ƃ���ɂȂ�܂��ˁB
13. �⌾���́A��x�������ύX�ł��܂��H
�@�������A
�⌾���́A���x�ł����������ł��܂��B
�@�P�� �i �Ă������E����ȍ~�͖����ɂ��邱�� �j �����肷�邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�̕ω� �i �Ƒ��\���A���Y�̑����A�C�����̕ω��Ȃ� �j �ɉ����āA
�V�����⌾�����쐬���邱���ł��܂��B
�@�܂��A�A�b�v�f�[�g�����ق����A�������܂����ˁB
�@����ɂ���āA
�ȑO�̈⌾���͓P�ꂽ��A�V�������e���D�悳�ꂽ�肵�܂��B
�@�������A
�ǂ̈⌾�����ŐV�ŗL���Ȃ̂��m�ɂ��Ă������Ƃ��d�v�ł��B
14. �⌾���̕ۊǂ́A�ǂ���������ł����H
�@���M�؏��⌾�̏ꍇ�́A
������ő�ɕۊǂ��܂��B
�@�܂��́A
�@���ǂ� �u ���M�؏��⌾���ۊǐ��x �v �𗘗p���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�����؏��⌾�̌��{�́A
���ؖ���ŕۊǂ���܂��B
�@����ŕۊǂ���ꍇ�́A������j���A
������̃��X�N���Ȃ��ꏊ�ɕۊǂ��܂��B
�@�Ȃ����A���Ƒ��ɕۊǏꏊ��`���Ă������Ƃ���ł��B
���d�̏�ɁA�z���ɓ���Č��J���Ă���l�����܂����ǂˁB
15. �@���ǂ� �u ���M�؏��⌾���ۊǐ��x �v �Ƃ́H
�@�@���ǂ��A
�⌾����ۊǂ��Ă���鐧�x�ł��B
�@���M�؏��⌾�́A
������U���̃��X�N�����炷���Ƃ��ł��܂��B
�@�������A
���e�͒��ׂ܂���̂ŁA�@�I�ɗL���Ƃ͌���܂����B
�@�����܂ł��A�ۊǂ��邱�Ƃ��ړI�ł��B
�@�ۊǂ��ꂽ�⌾���́A
�ƒ�ٔ����ł̌��F���s�v�ɂȂ郁���b�g������܂��B
�@�쐬�͂����g�ōs���K�v������܂����A
�ۊǂ̈��S���͍��܂�܂��ˁB
�f�����b�g�́A���e���L�����͕ۏ���Ȃ����Ƃł��ˁB
16. �⌾���쐬�ɂ������p�́A�ǂ̂��炢�ł����H
�@���M�؏��⌾�������ō쐬����ꍇ�́A
��{�I�ɔ�p�͂�����܂��� �i �p����Ȃǎ���̂� �j�B
�@�@���ǂ̕ۊǐ��x�𗘗p����ꍇ��
�萔����������܂��B
�@�����؏��⌾�́A
���Y�̊z����e�ɉ����Č��ؖ���̎萔����������܂��B
�@�܂��A
�ٌ�m��s�����m�Ɉ˗�����ꍇ�͕ʓr���ƕ�V���������܂��ˁB
17. �⌾���s�� �i �⌾������������ �j �Ƃ́A���ł����H
�@�⌾���s�҂Ƃ́A
�⌾���̓��e���������邽�߂ɕK�v�Ȏ葱�����A
���ۂɍs���l�̂��Ƃł��B
�@�����葱���͕��G�ŁA���낢��ȏ��ɏo�����Ȃ��Ȃ�܂���B
�@���Ƃ��A
��s�֍s���ĉ��葱���Ȃǂ��A���ۂɍs���܂��B
�@�����l�ł���O�� �i �ٌ�m�A�s�����m�Ȃ� �j �ł��w��ł��܂��B
�@�⌾���s�҂����邱�ƂŁA
���G�ȑ����葱�����X���[�Y�ɐi�݂܂���B
�⌾�҂̈ӎv���A�m���Ɏ�������₷���Ȃ�܂��ˁB
18. �⌾���s�҂́A�K���w�肵�Ȃ�������܂��H
�@�K�������A
�w�肷��K�v�͂���܂���B
�@�������A
�w�肷�邱�Ƃő����葱�����A
���ɃX���[�Y�ɐi�݂܂��B
�@���ɁA
���Y�̎�ނ������ꍇ
�����l����������ꍇ
�����l�ȊO�ɍ��Y���₵�����ꍇ
�Ȃǂɂ́A�⌾���s�҂̎w����������߂��܂��B
�@�Ȃ��Ȃ�A
���ׂĂ̎葱���̑�\�҂ɂȂ邩��ł��B
19. �◯�� �i ����イ�Ԃ� �j �Ƃ́A���ł����H
�@�◯���Ƃ́A
�Z��o���ȊO�̖@�葊���l�ɕۏႳ��Ă���A
�Œ���̑��������̂��Ƃł��B
�@�Ⴆ�A
�S���Y�����̐l�Ɉ②����⌾�������Ă��A
�◯����N�Q �i ���� �j ���ꂽ�����l�́A
�◯���𐿋����邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�����I�ɂ́A��������l���ٔ����āA
�������o���Ă��炤���Ƃ��K�v�ł��B
�@�⌾�����쐬����ۂ́A
�◯���ɂ��z�����邱�Ƃ��g���u���h�~�ɂȂ���܂��B
20. �◯����N�Q����⌾���́A�����ł����H
�◯����N�Q����⌾���ł��A
���ꎩ�̂������ɂȂ�킯�ł͂���܂���B
�@�������A
�◯����N�Q���ꂽ�����l�́A���̐N�Q���ꂽ�����ɂ��āA
�◯���N�Q�z���������s�g���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�u �ٔ����ɑi���邱�Ƃ��ł��� �v �̂ł����āA
�u ���Ȃ���Ȃ�Ȃ� �v ���̂ł͂���܂���B
�@���̐���������ƁA
��Y���������G�ɂȂ�\�������邽�߁A�쐬���ɂ͒��ӂ��K�v�ł��B
�@�w �P�~�����Ȃ� �x �Ƃ����A�⌾�������܂��B
�@�������A
�c���ꂽ����̍Ȃ�q�����A���̍ٔ��͂��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�c���ꂽ���Ƒ��̍K�����l���邱�Ƃ��A
���Ȃ��ɂ����ł��Ȃ����Ƃł���ˁB
21. �����N�ł��A�⌾���͍��܂����H
�@�͂��A
15�Έȏ�ł���Έ⌾�����쐬���邱�Ƃ��ł��܂���B
�@�܂�A
��l�����ŁA�@�I�ɗL���Ȉ⌾���쐬�ł��܂��B
�@�������A���̓��e���L���ł��邱�Ƃ͕ʂł���B
�@�܂�A
�⌾�\�� �i �����̍s�ׂ̌��ʂ𗝉��ł��锻�f�\�� �j ���A�K�v�ł��ˁB
�@�����N�̕����⌾�����쐬����ۂ́A
���̔��f�\�͂ɂ��ď\���Ȓ��ӂ��K�v�ł��B
�@�����N�̈⌾���́A���̕K�v�����ƂĂ��d�v�ȏꍇ�������ł��B
���ǁA�g���Ȃ������ƂȂ�Ȃ��悤�ɏ\���Ȓ��ӂ��K�v�ł��ˁB
22. �F�m�ǂɂȂ�����A�⌾���͍��܂��H
�@�F�m�ǂ́A���x�ɂ��܂��ˁB
�@�⌾�����쐬���鎞�_ �i ���S�̎��_�ł͂���܂��� �j �ŁA
�@�u �����g�̍��Y��Ƒ��\�� �v
�@�u �⌾�̓��e�𗝉��� �v
�@�u ���f�ł���\�́i�⌾�\�́j������ �v
���Ƃ��K�v�ł��B
�@�F�m�ǂ̏Ǐi��ł���ꍇ�A
�L���Ȉ⌾�����쐬���邱�Ƃ͓���ł��傤�ˁB
�@���̂��߁A���C�Ȃ����ɍ쐬���Ă������Ƃ��d�v�ł���B
���{�l�₲�Ƒ��̕s���ɓ�����悤�ɂ��āA�⌾�����T�|�[�g���܂��B
23. �v�w�ňꏏ�ɁA�u ��̈⌾�� �v ���쐬�ł��܂����H
�@�������A�ł��܂���B
�@�v�w�ł����Ă��A
�u ��̈⌾�� �v �������ō쐬���邱�Ƃ͂ł��܂���B
�@�⌾���́A
�u �P�ƍs�� �i����ǂ��������j �v �Ƃ���Ă��܂��B
�@�K���A��l�ЂƂ肪�ʂɍ쐬����K�v������܂��B
�@�Ȃ̂ŁA
�v�w���ꂼ��̈ӎv�d�����⌾�����A�쐬�������ꍇ�́A
���ꂼ�ꂪ�A�ʁX�Ɉ⌾�����쐬���邱�ƂɂȂ�܂��ˁB
24. �⌾���ŁA�y�b�g�̐��b�𗊂߂܂����H
�@�͂��A�����S���������B
�@�⌾���ɁA
�y�b�g�̐��b�Ɋւ����]��t�������Ƃ��ċL�ڂł��܂��B
�@�y�b�g�̐��b�����Ă����l�ɑ��āA���Y���②�������ɁA
���b���˗������肷����@������܂���B
�@�������A�y�b�g���̂ɍ��Y���₷���Ƃ͂ł��܂����B
�@��̓I�ɂǂ����Ăق������L���A
�⌾���s�҂ɂ��̎�����������Ƃ��l�����܂��ˁB
25. �⌾���ƃG���f�B���O�m�[�g�́A�������̂ł����H
�@�������A�قȂ�܂��B
�@�⌾���́A
�@�I�Ȍ��͂������ނł���A
�@�Œ�߂�ꂽ�`���ɑ����č쐬����K�v������܂��B
�@����A�G���f�B���O�m�[�g�́A
���Y���A�A����A��Â���̊�]�A
���V�̊�]�Ȃǂ����R�ɏ����c�����̂ł��B
�@�@�I�Ȍ��͂͂���܂��A
���Ƒ��ւ̏��`�B�╉�S�y���ɖ𗧂��܂��B
�@�܂��A�⌾�قnj��ꂵ���Ȃ��A�C�y�ɏ�����̂������ł��B
��i���� �i ���ꂪ���\��ςł� �j �Ȃǂ́A�⑰�ւ̐��_�I���S�����点�܂���B
26. �⌾���́A�����ŏ����̂���Ԃł����H
�@�����g�ŏ������Ƃ͉\�ł���B
�@�������A
�@�I�ɗL���Ȉ⌾�����쐬����ɂ́A���m�����K�v�ł��B
�@�u �`���s���Ŗ����ɂȂ����� �v
�@�u ���e�������܂� �v
�������肷��ƁA�������ăg���u���̌����ɂȂ肩�˂܂���ˁB
�@�Ⴆ�A
�u �Z��Œ��ǂ������Ȃ��� �v �ƌ����Ă��A�����葱�����悤���Ȃ�����ł��B
�@�m���Ɉӎv�������������̂ł���A
���� �i �s�����m�A�ٌ�m�A�i�@���m�Ȃ� �j ��
���k���邱�Ƃ��������߂��܂��B
27. �⌾���쐬�̑��k�́A�N�ɂ�������ł����H
�@�⌾���쐬�́A
�s�����m�A�ٌ�m�A�i�@���m�A���ؖ���Ȃǂő��k�ł��܂��B
�@���ꂼ�꓾�ӕ�����p���قȂ�܂��B
���Y�����⑊���葱���S�ʂ���������Ȃ�s�����m��ٌ�m�A
�o�L�葱��������ɓ����Ȃ�i�@���m�A
�m���Ȍ����؏��⌾��]�ނȂ���ؖ���Ƃ������I����������܂��ˁB
�@�����Ȃǂł́A
�������k��𗘗p���ēK�C�҂������ꂱ�Ƃ��������߂��܂��ˁB
28. �⌾���쐬�ɂ́A�ǂꂭ�炢�̎��Ԃ�������܂����H
�@���M�؏��⌾�ł���A
�����g�ō쐬���鎞�Ԃɂ��܂��B
�@�����؏��⌾�̏ꍇ�A
���ؖ���Ƃ̑ł����킹��K�v���ނ̏������Ԃ��܂߂�ƁA
���T�Ԃ��琔���������邱�Ƃ�����܂��B
�@���e�̕��G����A���ƂƂ̘A�g�ɂ���Ă����Ԃ͕ϓ����܂���B
�@�]�T�������ď������n�߂邱�Ƃ���ł��ˁB
�@���M�؏��⌾�ŋ}������̂��ŁA
���������Ă���A�����؏��⌾�����쐬���邱�Ƃ��ł��܂���B
29. �⌾���쐬�ɁA�K�v�ȏ��ނ͉��ł����H
�@�⌾���̎�ނɂ���ĈقȂ�܂����A
��ʓI�ɂ́A
�⌾�҂̖{�l�m�F���� �i �^�]�Ƌ��Ȃ� �j�A
��ӓo�^�ؖ����A
����A
���Y�Ɋւ��鏑�� �i �s���Y�̓o�L�듣�{�A�a�����̎c���ؖ����Ȃ� �j�A
�����l�Ƃ̊W�������ːГ��{
�Ȃǂ��K�v�ł��B
�@�܂��A
�L�����Ԃ�����ꍇ������̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B
�����؏��⌾�̏ꍇ�́A�ؐl�̐g���ؖ����Ȃǂ��K�v�ɂȂ�܂��B
30. �⌾���ŁA��t�͂ł��܂����H
�@�͂��A�ł��܂��B
�@�⌾����ʂ��ē���̒c�� �i ���P�c�́A�w�Z�@�l�Ȃ� �j �ɍ��Y����t����A
�u �②��t �i���������Ӂj �v���\�ł���B
�@�Љ�v���������Ƃ����A�ӎv�������������ł��B
�@�⌾���́A
���O�̑z�����Љ�ɖ𗧂Ă邽�߂̗L���Ȏ�i�ƂȂ�܂���B
�@��t����]����ꍇ�́A
������̒c�̖����̓I�ȍ��Y�m�ɋL�ڂ���K�v������܂��ˁB
�@�Ⴆ�A���{�ԏ\���ЁA���j�Z�t����Ȃǂł��B
�@�܂��A�y�b�g�̕ی�c�́A�n��̒c�̂Ɋ�t�����������܂���B
�@�������A
�y�n�Ȃǂ͎t���Ȃ��c�̂�����A���O�̊m�F���K�v�ł��ˁB
31. �⌾���� �u �t������ �i�ӂ������j�v �Ƃ��āA���������܂����H
�@�t�������́A�@�I�Ȍ��͂͂���܂���B
�@�������A
���Ƒ��ւ̊��ӂ̋C�����A
�⌾�����쐬�������R�A
�c���ꂽ���Ƒ��ւ̊肢�A
���V�Ɋւ����]�ȂǁA
���Ȃ��̑z�������R�ɏ����c���镔���ł��B
�@����ɂ��A�⌾�̈Ӑ}���`���₷���Ȃ�A
���Ƒ����⌾�̓��e���A
����₷���Ȃ���ʂ����҂ł��܂��B
�@�⌾���ɏ������Ԃ́A�ŏ��ł��Ō�ł��A
�ǂ���ł����R�ł��B
�Ōゾ����ƌ����āA
�����⍦�݂������̂́A��߂Ă��������ˁB
32. �⌾�����A�������������ꍇ�͂ǂ��Ȃ�܂����H
�@�����̈⌾�����A
������ꍇ������܂��ˁB
�@���̎��͌����Ƃ��āA
���t����ԐV�����⌾�����L���ƂȂ�܂��B
�@�������A
�O�̈⌾���Ɠ��e���������Ȃ������́A
�O�̈⌾�����L���Ƃ���܂���B
�@���̂��߁A
�V�����⌾�����쐬����ۂɂ́A
�ȑO�̈⌾�������ׂēP��|�L����ȂǁA
�����܂������Ȃ������Ƃ��d�v�ł��ˁB
33. �⌾���ɁA�L�������͂���܂����H
�@�⌾�����̂ɁA�L�������͂���܂���B
�@��x�쐬���ꂽ�⌾���́A
�⌾�҂��P�Ȃ�����A���̌��͂����������܂��B
�@�������A
�⌾�҂̏���Y�A�@���̉����Ȃǂɂ��A
���e������ɍ���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ����X����܂��B
�@���x�ł����������܂��̂ŁA
����I�Ɍ��������s�����Ƃ��������߂��܂��B
�A�b�v�f�[�g���邱�ƂɁA�����͂���܂���ˁB
34. �⌾�����쐬���Ȃ��ƁA���Y�����̂��̂ɂȂ�܂����H
�@�������A�����Ƃ�����܂���B
�@�⌾�����Ȃ��ꍇ�ł��A
�����l��������̑����l�ɍ��Y�������p����܂���B
�@�����l���N�����Ȃ��ꍇ�́A
�ŏI�I�ɍ��ɂɋA�����邱�ƂɂȂ�܂��ˁB
�@�⌾���́A
���Ɏ���邱�Ƃ��A�h�����߂̂��̂ł͂���܂����B
�@���Ȃ��̈ӎv�œ���̌l��c�̂ɍ��Y���A
�m���Ɉ����p�����邽�߂ɍ쐬������̂ł���B
�����l�����Ȃ��ꍇ�ł��A�⌾���͕K�v�ł��ˁB
35. �⌾���͌����؏��łȂ���A���͂��Ȃ��ƕ����܂������H
�@����́A����ł��B
�@���M�؏��⌾��閧�؏��⌾���A
�@�I�ɗL���Ȍ`���ō쐬����Ă���A
�����؏��⌾�Ɠ��l�Ɍ��͂�����܂���B
�@�������A
�����؏��⌾�͌��ؐl���쐬���邽�ߖ@�I�ȕs�����Ȃ��A
���{���ۊǂ���邽�߁A�ł��m�����������Ƃ���Ă��܂��ˁB
�@�⌾���́A�P��ނ�������Ă͂����Ȃ����܂�͂���܂���B
�����̈⌾����g�ݍ��킹�邱�Ƃ��A�ł��܂���B
36. �⌾�����쐬�������Ƃ�N���ɓ`����ׂ��ł����H
�@�͂��A��������ł��ˁB
�@���ɁA�⌾�����쐬�������Ƃ�M���ł��邲�Ƒ���A
�⌾���s�҂Ɏw�肵�����ɂ͓`���Ă������Ƃ������������߂��܂��B
�@�⌾���̑��݂�m��Ȃ���A
�����葱����������A
�⌾����������Ȃ������肷��\��������܂���B
�@�������A
���M�؏��⌾�œ��e��閧�ɂ������ꍇ�́A
�ۊǏꏊ������`���Ă����Ȃǂ̍H�v���K�v�ł��ˁB
�@�܂��A���J���Ă����͂��Ȃ��Ȃ���̂ł�����܂����B
���ۂɁA���d�̏�Ɋz���ɓ���āA�����Ă���l�����܂���B
37. �⌾���쐬��ɍ��Y���A�ϓ������ꍇ�͂ǂ��Ȃ�܂����H
�@�⌾���쐬��ɍ��Y���ϓ����Ă��A
�⌾���������ɂȂ�킯�ł͂���܂���B
�@�������A
�⌾���ɋL�ڂ��ꂽ���Y����������Ă��܂�����A
�V�������Y���擾�����肵���ꍇ�́A
�⌾���̓��e�ƌ�����Ȃ��Ȃ�A
���Ȃ��̈ӎv�����S�ɔ��f����Ȃ��\��������܂���B
�@���Y�ɑ傫�ȕω����������ꍇ�́A
�⌾���̌��������������܂��傤�B
�@������ύX���Ă��A�N�ɂ��{���邱�Ƃ͂���܂����B
�@�A�b�v�f�[�g�ɂ́A�����͂���܂���ˁB
�������邱�ƂȂ��A
�����_�ł̂��Ȃ��̋C������\�����Ƃ��ł��܂���B
38. �⌾�����쐬�������Ƃ���������ꍇ�A�ǂ���������ł����H
�@�⌾�����쐬�������Ƃ����������A
�S�ς�肵���肵���ꍇ�́A
���ł��P����A
�V�����⌾�����쐬���������肷�邱�Ƃ��ł��܂���B
�@�⌾���͂P�T���珑����ƌ������Ƃ́A
���x�ł��A����������Ƃ̈Ӗ��ł���B
�@�V�����⌾�����쐬����ۂ́A
�ȑO�̈⌾�������ׂēP��|�m�ɋL�ڂ��邱�ƂŁA
�ӎv�̏Փ˂�h�����Ƃ��ł��܂��B
���S���āA�����g�̈ӎv���C�����邱�Ƃ��\�ł��B
39. �⌾���ŁA���ɍ��Y���₷���Ƃ͂ł��܂����H
�@�͂��A
�⌾���ő��ɒ��ڍ��Y���₷���Ƃ��ł��܂��B
�@����� �u �② �i�������j�v �ƌ����܂��B
�@���͒ʏ�A�@�葊���l�ł͂Ȃ����߁A
�⌾�����Ȃ�����Y����邱�Ƃ͂ł��܂����B
�@�⌾���ŁA���Y���p���ӎv�m�ɂ��܂��傤�B
�@�②���邱�ƂŁA
�����g�̊�]�ʂ�ɑ�ȑ��ɍ��Y���^���邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂���B
40. �⌾���Ő��b�ɂȂ����l�ɁA���Y���₷���Ƃ͂ł��܂����H
�@�͂��A�ł��܂��B
�@�����b�ɂȂ������F�l��m�l�ȂǁA
�����l�ł͂Ȃ����ɂ��A�⌾����ʂ��č��Y���₷���Ƃ��ł��܂���B
�@����� �u �② �i�������j�v �ɂ�����܂��ˁB
�@���ӂ̋C���������Y�Ƃ����`�œ`�������ꍇ�A
�⌾�����쐬���邱�Ƃ��L���Ȏ�i�ƂȂ�܂��B
�@�������A
������̎�����Z���𐳊m�ɋL�ڂ��邱�Ƃ��d�v�ł��B
41. �⌾���́A���Ƃɗ��ނׂ��ł����H
�@�����g�ō쐬���邱�Ƃ��\�ł����A
�`���s���Ŗ����ɂȂ�����A
���e�������܂��Ńg���u���ɂȂ����肷�郊�X�N������邽�߂ɂ́A
���ƂɈ˗����邱�Ƃ��������߂��܂��ˁB
�@�Ⴆ�A
�u �Z��Œ��ǂ� �v �Ƃ�
�u �S���Y���� �v
�Ȃnj����Ă������悤���Ȃ��ł�����ˁB
�@���Ɍ����؏��⌾�́A
���Ƃ��֗^���邽�ߊm�������������S�ł���B
���Ƃ́A���Ȃ��̏ɍ��킹���œK�ȃA�h�o�C�X����A
�m���Ȉ⌾���쐬���T�|�[�g���܂���B
42. �⌾���́A���F �i ����ɂ� �j �Ƃ͉��ł����H
�@�⌾���̌��F�Ƃ́A
�ƒ�ٔ����������l�S���̗�����̂��ƁA
�⌾���̓��e���m�F���A�U����ϑ���h�����߂̎葱���ł��B
�@���M�؏��⌾��閧�؏��⌾�́A
���̌��F�葱�����o�Ȃ��ƁA�J��������A
�����葱���Ɏg�p�����肷�邱�Ƃ��ł��܂���B
�@�����؏��⌾�́A���F���s�v�ł���B
43. �⌾���ƁA�����ł̊W�͂���܂����H
�@�⌾�������邱�ƂŁA
�����ł̌v�Z���@���ς��킯�ł͂���܂���B
�@�������A
�ߐő���l�������⌾�����쐬���邱�Ƃ͉\�ł��B
�@�Ⴆ�A
����̍��Y�����̑����l�Ɉ②���邱�ƂŁA
���K�͑�n���̓���Ȃǂ��K�p����₷���Ȃ�ꍇ������܂��B
�@�ŗ��m�ƘA�g���Ȃ���A
�����I�ȑ�������������邱�Ƃ��d�v�ł��B
�@�������k��𗘗p���āA
�ŗ��m����ɑ��k���邱�Ƃ���n�߂Ă��������B
44. �⌾���ɁA��ÂɊւ����]�͏����܂����H
�@�͂��A�����܂��B
�@�⌾���ɉ������Â̊�]��A
�������Ɋւ����]�Ȃǂ�t�������Ƃ��ď����c�����Ƃ͉\�ł���B
�@�@�I�ȋ����͂͂���܂��A
���Ȃ��̈ӎv���Ƒ����ÊW�҂ɓ`����d�v�Ȏ肪����ƂȂ�܂��ˁB
���m���Ɉӎv�\���������ꍇ�́A
�u �������錾�����؏� �i ����������؏��j�v �Ȃǂ�
���ؖ���ŕʓr�쐬���邱�Ƃ������ł��܂���B
�@�������錾�����؏��́A�{�l���錾����悭�A
�ؐl���K�v�Ȃ���y�ɍ쐬�ł��܂��B
45. �⌾���͂ǂ��ɑ��k����A�����쐬�ł��܂����H
�@��p��}�������ꍇ�́A
�����g�Ŏ��M�؏��⌾���쐬������@������܂��ˁB
�@�������A
�@�I�ȗL�������l����ƁA���Ƃւ̑��k�͕K�{�ł���B
�@�����؏��⌾�̔�p�͌��ؐl�萔���߂Œ�߂��Ă���A
���ƕ�V�͊e�������ňقȂ�܂��B
�܂��͖������k�Ȃǂ𗘗p���āA
��p�ƃT�[�r�X���e���r�������Ă݂܂��傤�B
46. �⌾���̓��e���A�閧�ɂ��Ă������Ƃ͂ł��܂����H
�@�閧�ɂ������ꍇ�́A
�閧�؏��⌾��I��������@������܂��B
�@�������A
���e�̗L�����܂ł͌��ؐl���m�F���Ȃ����߁A
�����g�Ŗ@�I�ȕs�����Ȃ������m�F����K�v������܂��B
�@�ł��m���ɓ��e��閧�ɂ��A
�@�I�ȗL������ۂ������ꍇ�́A
�����؏��⌾���쐬���A
�M���ł���l�� �u �⌾�����쐬�������� �v �� �u �ۊǏꏊ �v ������`���Ă����̂������I�ł��B
47. �⌾���쐬��A�Ƒ��ɒm�点��^�C�~���O�͂��ł����H
�@����́A���Ƀf���P�[�g�Ȗ��ł��ˁB
�@��ʓI�ɂ́A�⌾���̑��݂ƕۊǏꏊ�́A
�M���ł��邲�Ƒ���⌾���s�҂ɓ`���Ă������Ƃ���������܂��B
�@�������A
���e�܂Ő��O�ɓ`���邩�ǂ����́A
���Ƒ��̊W����⌾�̓��e�ɂ��܂��ˁB
�@���ɓ��e�����G�ȏꍇ��A
���Ƒ��Ԃňӌ��������ꂻ���ȏꍇ�́A
���ƂƑ��k���ă^�C�~���O���������܂��傤�B
48. �⌾�����Ȃ��Ă��A�����葱���͂ł��܂����H
�@�͂��A
�⌾�����Ȃ��Ă������葱���͉\�ł���B
�@���̏ꍇ�́A
�@�葊���l�S���Řb������ �u ��Y�������c �i������Ԃ��傤���j�v ���s���A
���Y�̕����������߂邱�ƂɂȂ�܂��ˁB
�@�������A
�S���̍��ӂ��K�v�Ȃ��߁A
�s���s���҂�T������A
���Ԃ��Ԃ�����������A
�ӌ��̑Η�����g���u���ɔ��W�����肷�郊�X�N�����܂�܂��ˁB
�⌾������������A�葱���̓X���[�Y�ɐi�݂܂���B
49. �⌾���쐬���A�}���ׂ��^�C�~���O�͂ǂ�Ȏ��ł����H
�a�C�Ȃǂő̒�������ꂽ���A
�傫�ȍ��Y�̕ϓ������������A
�Ƒ��\�����ς������ �i �����A�o�Y�A�����A�č��Ȃ� �j�A
���Ə��p���l���Ă��鎞�A
�����Ă����g������ɂȂ�A
�����̔��f�\�͂ɕs���������n�߂����Ȃǂ��A
�⌾���쐬���}���ׂ��^�C�~���O�ƌ����܂��B
�@�������A
�P�T����⌾���쐬�ł���Ƃ������Ƃ́A
�ǂ̃^�C�~���O�ł������Ƃ������Ƃł���B
���C�Ȃ����ɁA
�����g�̈ӎv�m�ɂ��Ă������Ƃ���������ł��ˁB
50. �⌾���Ńg���u���ɂȂ�����A�ǂ���������ł����H
�@�⌾���������Ńg���u���ɂȂ��Ă��܂����ꍇ�́A
�܂��͐��Ƃł���ٌ�m��s�����m�ɑ��k���邱�Ƃ��������߂��܂��B
�@�ɉ����āA
�⌾���̉��߂̒����A
��Y�������c�̂�蒼���A
���邢�͈◯���N�Q�z�����ȂǁA
�@�I�Ȏ�i���u����K�v������܂��B
�@�����ɐ��Ƃɑ��k���邱�ƂŁA
���̉����Ɍ����čœK�ȃA�h�o�C�X�ƃT�|�[�g���邱�Ƃ��ł��܂���B
�܂��A�X���[�Y�ɑ������������҂ł��܂��ˁB